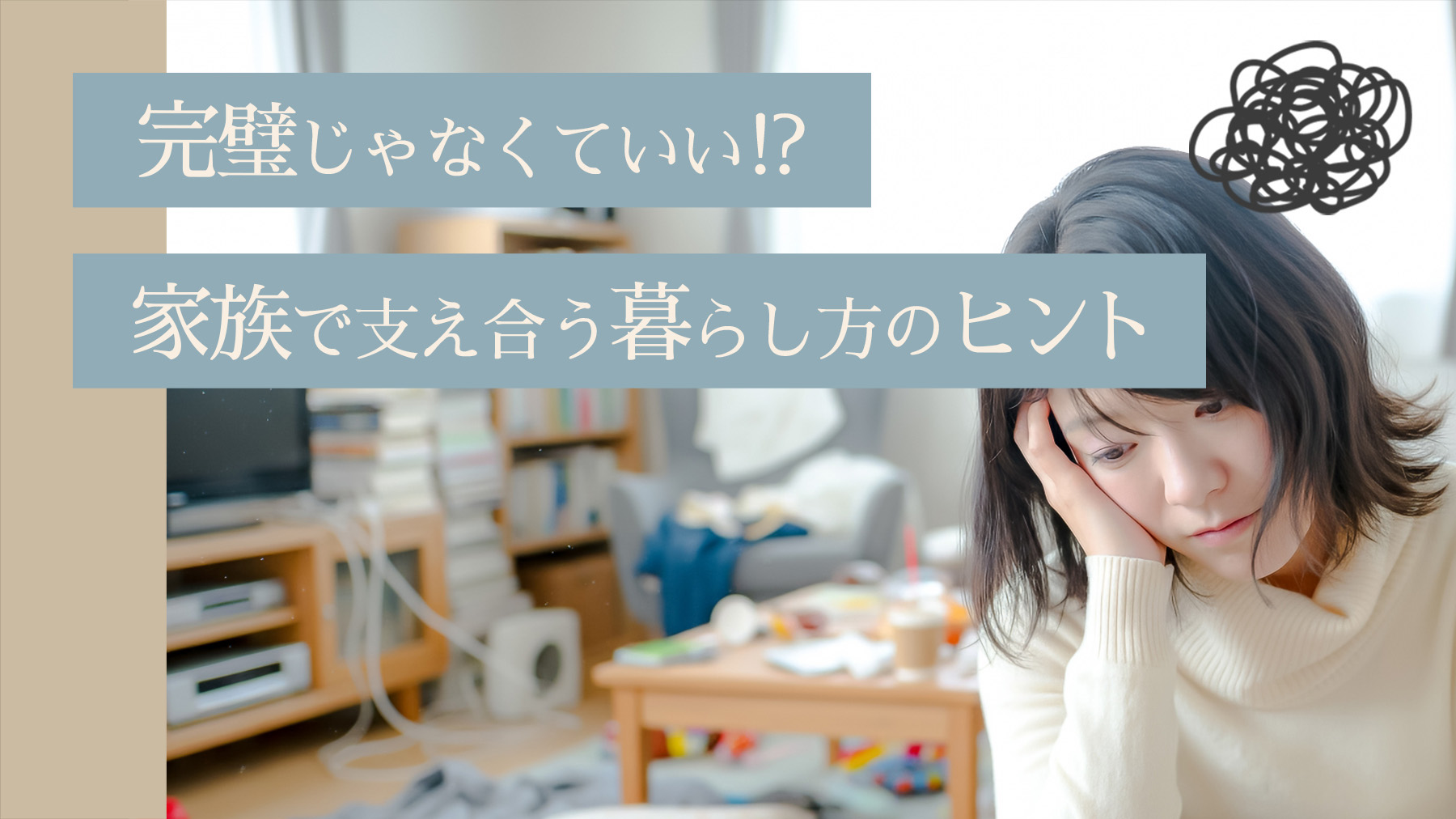はじめに|「時間が足りない」子育て家族の現実
ライターのまいです。地域や暮らしの魅力を丁寧に伝え、読者の皆さまに信頼できる情報をお届けしています。
2025年、日本に初の女性総理・高市総理が誕生しました。
就任会見での言葉。
「ワークライフバランスという言葉を捨てます」
「働いて、働いて、働いて、働いて、働きます」
この力強いフレーズに、勇気をもらった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
でも現実の家庭では、「働いて働いて…もうクタクタ!」というのが本音かもしれません。
朝は家族全員が慌ただしく動き回り、日中は仕事、夜は家事と育児。気づけば、自分の時間なんてほとんどない。帰宅してちょっと休憩と思ったらソファーから動けない!夕飯を作る気力がない!
そんな日々を過ごすママやパパ、そして家族みなさんへ。 この記事では、「頑張りすぎない両立のコツ」と「家族で支え合う時間の作り方」をお伝えします。
1. 仕事と家庭、どちらも「完璧」は目指さない

働くママ・パパの多くが抱える悩み…
「どっちも中途半端かもしれない」「ちゃんとできていない気がする」。
でも、完璧を目指す必要はありません。
家族が笑っていられるなら、それで十分です。
「できるときに、できる範囲で。」
これを家族みんなの合言葉にしてみましょう。
掃除ロボットを活用したり、冷凍食品や宅配弁当に頼ったり。
パパが洗濯を担当して、ママが子どもの宿題を見るなど、
少しずつ役割を見直すことで、みんなの負担が一段と軽くなります。
高市総理のような力強さも魅力的ですが、家庭では柔軟なチームワークが最も重要です!
家族みんなで「助け合う暮らし」を育てていきましょう。
2. 子どもの体調不良…急な休みにどう対応する?

子どもは、突然の発熱や体調不良がつきもの。
そんな時、仕事の調整や職場への連絡で、焦ったり申し訳なく感じたりすることもありますよね。
けれど、家族の健康を優先することは、何よりも大切なこと。
無理をして働くより、しっかり看病してあげる方が、結果的にみんなの安心につながります。
日頃からチームで業務の流れを共有しておくことや、引き継ぎメモを用意しておくなど、事前の準備をしておけばいざという時にも落ち着いて対応できます。
在宅勤務や時短制度を上手に活用するのもおすすめです。
「ひとりで抱え込まない」こと。 それが、家庭も仕事も長く続けていくためのいちばんのコツです。
3. 長期休暇シーズン、どう乗り切る?

春休み、夏休み、冬休み。
子どもたちの長期休暇は、働く家庭にとってなかなかのハードル。
学童保育や祖父母のサポートを活用しながら、パパ・ママで協力し合うことが大切です。
「午前はママ、午後はパパ」など、少しの調整でずいぶんラクになります。
また、子どもに“お留守番スキル”を育てるチャンスでもあります。
一緒に安全ルールを話し合い、「1日の予定表」を作っておくと安心です。
ママやパパが仕事を頑張っている姿を見せることは、子どもにとって最高の学びです。
家族みんなで力を合わせて、長期休暇を“チーム戦”で乗り切りましょう。
4. 我が家の失敗談

ここで、我が家の失敗談をひとつお話しします。
長女が2年生になったばかりの春、試しに「2時間のお留守番チャレンジ」をしてみました。
レベル1〜3に分けた折り紙ミッションと、守ってほしい簡単なお約束をイラスト入りのお手紙にしておき、私と主人にメッセージを送れるようにタブレットも設定して準備は万端。仕事中もこまめにメッセージをチェックし、返信を続けていました。
ところが、帰宅してみるとテーブルの上にはレベル3の折り紙が山のように積まれていて、長女はどこか不安そうな表情でした。寂しさを紛らわせようと一生懸命折った大量の折り紙を見て、家族で「まだお留守番は早かったかもね」と反省会。たくさん褒めて「ごめんね、よくがんばったね」とぎゅっと抱きしめました。
年齢だけで判断してしまいがちですが、その子にとっては心の負担になる場合があると痛感した出来事でした。年齢や性格に合わせて、少しずつチャレンジの内容や時間を調整することの大切さを、改めて学んだ日でもあります。
5. 限られた時間でも心が通う関わり方

忙しいと、つい「ちゃんと向き合えてないな」と感じてしまうもの。
でも、大切なのは“量”より“質”です。
寝る前の10分だけでも、「今日一番楽しかったこと、何?」と話すだけで、子どもの表情は豊かになります。
朝のハイタッチや、出かける前の「いってらっしゃい」の笑顔も、立派なコミュニケーション。
そして、ママとパパが仲良く話している姿を見せることも、子どもにとっての安心です。
家族のあたたかい空気が、子どもの心の土台をつくります。
6. 忙しくてもできる愛情表現のコツ

仕事で疲れて帰った夜。
言葉をかける元気がなくても、「スキンシップ」で伝える愛情があります。
ハグ、頭をなでる、手をつなぐ。それだけで子どもは安心します。
寝る前の「おやすみタッチ」や、朝の「いってらっしゃい10秒ハグ」
触れるだけで、「今日も大好き」が伝わります。
パパやママ同士でも、「おつかれさま」「ありがとう」と声をかけ合うだけで、気持ちがほどけます。
家族の中の“ありがとう”が、毎日のエネルギー源になるのです。
7. ママ・パパのメンタル維持法

家族を笑顔で支えるには、ママもパパも自分を満たす時間が必要です。
朝10分のコーヒータイム、通勤中の好きな音楽、たまの一人ランチ。
どんな小さなことでも、心を整える“リセット時間”になります。
高市総理が掲げる「持続可能な働き方」は、家庭にも当てはまります。
“持続可能な家族の形”とは、みんなが無理をしすぎない暮らし。
「助けて」「お願い」と言える関係こそが、最強のチームです。
そして、くだらないことでも話せる友人や会社の同僚。ゆるいつながりも大切に。
共感の一言や、励ましのコメントが、心を軽くしてくれます。
まとめ|家族みんなの笑顔が、いちばんの幸せ!
女性初の総理誕生というニュースは、社会に新しい希望をもたらしました。
「女性が働く」ことが特別ではなく、“家族みんなで支え合いながら生きていく”時代が始まっています。
でも、誰かと比べる必要はありません。
ママにはママのペースがあり、パパにもパパの形があります。
立ち止まっても、休んでも、それも前に進む一歩です。
高市総理の言葉「働いて働いて働いて…」
前向きな姿勢は、多くの人に勇気を与えます。
この力強い想いを、家庭では“みんなで力を合わせるエネルギー”として受け取りたいですね。
――「助け合って笑って協力して」
子どもは、ママやパパ、家族みんなの背中を見て育ちます。
頑張る姿も、迷う姿も、寄り添い合う姿も、すべてが“愛”の形。
今日も、ママもパパも、そして子どもたちも。
それぞれの笑顔が、家庭という小さな社会をあたためています。
完璧を目指すより、「一緒に笑える時間」や「共感できる時間」を大切に。
その小さな積み重ねが、きっと家族みんなの幸せにつながっていきます。
迷いながら、試行錯誤しながら、助け合いながら「家族」という最強のチームを日々育てていきましょう!